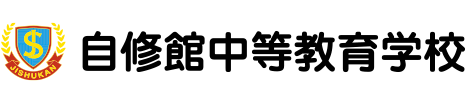生徒会選挙
2025.11.26
学校長の部屋
生徒会選挙の立会演説会を実施しました。会長候補、後期課程生の本部役員候補はいずれも定数を超える立候補となり、今年は信任投票ではない、文字どおりの「選ぶ」選挙です。一部の候補者はインフルエンザ罹患のため後日演説を行うことになりましたが、形式をオンラインに切り替えての開催とし、第一会議室を会場に候補者が入れ替わり登壇しました。画面越しではあっても、会場には適度な緊張感が漂い、ひとり一人が真剣な眼差しで自らの言葉を紡いでいたのが印象的でした。
運営を担った選挙管理委員会の5年生は、これまで丹念に準備を重ね、当日の進行も滞りなく、候補者が主張をしっかり伝えられるよう細部まで心を配ってくれました。投票までの工程全体に見通しを持ちながらも肩の力は抜けており、責任感と落ち着きが同居する頼もしさを感じました。

各候補の公約は幅広く、日常の不便や課題をていねいに拾い上げたものばかりでした。たとえば、カフェテリアでの電子決済導入、グラウンドや屋上の昼休み開放、パーカーを制服の1アイテムに加える提案。生徒会からの情報発信を強化するための生徒会インスタや学校公式キャラクターの検討。いじめに立ち向かうピンクシャツデーへの参加提案。行事の見直しでは、スキー教室の復活、自修祭でのスマホ利用解禁、スポーツ大会でのクラスTシャツ作成許可など。そして、生徒が主体的に動ける環境づくり、意見箱の改善、生徒の声を生かした行事改革といった自治の拡充も語られました。どれも、生徒の思いを代弁し、学校を明るく風通しのよい場にしたいという願いに満ちています。教員の立場からも、この生徒たちと対話を重ね、学校生活の改善にとどまらず新しい価値を共に生み出したい、と強く感じました。

画面の向こう側では、投票する生徒たちが仲間の話に耳を傾け、熱心にメモを取る姿がありました。自分たちの代表を真剣に選ぼうとする態度は頼もしい一方で、どことなく受け身な空気が残っていることも否めません。生徒会活動や選挙は「主権者教育」として機能しているのか。実はこれは、先の参議院選挙を見つめた際にも覚えた感覚です。選挙はお祭りのような高揚感を帯び、盛り上がって見えるのですが、焦点が「誰が何をしてくれるか」に偏り、「自分はどう参画し、どう解決に関わるのか」という視点が弱くなりがちです。生徒会選挙でも、明確な争点が見えにくいと、身近な人柄や雰囲気、その場のノリで票が動き、投票後は活動への関心が薄れてしまう傾向があります。会長・役員が始業式や終業式、生徒総会、昼の放送で発信しても、十分なインパクトを残せていないのではないか、そんな自省が頭をもたげます。
これは、生徒会の仕組みそのものに欠陥があるというより、本校が選挙を「主権者教育」の機会としてどう設計し、どう学びにつなげるかという視点を、私たち教員が十分に持てていないからではないか。そう考え、次のような働きかけを計画的に進めたいと思います。
・現状と課題の可視化
自分や周囲が感じる学校生活の課題を班・クラスで共有し、合意形成のプロセスを体験する。
・情報の整理と比較
演説会のメモや選挙公報を基に、候補者の願い・施策をワークシートで整理し、自分の視点と照らし合わせる。演説前後で考えがどう変化したかを言語化する。
・投票基準の明確化
「意見が近いか」に加え、実行力、優先順位付け、説明責任への姿勢など複数軸で判断する。
・振り返りの定着
ロングホームルーム等で、選挙後も施策の進捗を追い、主体者としての関わり方を継続的に学ぶ。
志を持って立候補する生徒の背中を押し、挑戦する勇気を与えてくださる先生方の支えがあって、本校の生徒会選挙は脈々と続いてきました。当選後の地道な生徒会活動も、顧問の先生方をはじめ各学年の先生方の理解と助言・助力によって成り立っています。そのうえで、より多くの生徒が学校生活の改善・向上に主体的に関われるようにする。ひいてはそれが主権者としての在り方につながるようにする。そのための指導の余地は、まだまだ残されていると感じます。
生徒の未来のために、選挙を「続ける」だけでなく、「成長に生かす」。この原点に改めて立ち戻り、投票箱が閉じた後も対話を開き続ける学校でありたい。生徒と教職員が力を合わせ、ここ自修館から新しい学びの価値をともに創り出していきます。
☆校長Instagram『principal_of_jishukan』を始めました!

皆さんに自修館をより身近に感じていただけるよう、私の学校内外の日常を発信していきます。よろしければ、フォローをお願いします!